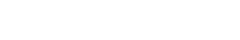| 概 要 |
1.開会挨拶
保健福祉部より挨拶
2.委員自己紹介
全員自己紹介
3.議事
① 令和7年度地域包括ケアシステムの構築に向けた取り組みの報告
地域包括支援センター職員より順次説明し、項目ごとに意見交換を実施する。
1)地域ケア会議について 報告 資料P2~
2)在宅医療看護・介護連携部会 報告 資料P9~
3)認知症施策推進部会 報告 資料P14~
4)介護予防事業 報告 資料P18~
5)協議体について 報告 資料P21~
【意見交換】
- 薬剤師会・病院・保険健康課:
Q.専門職におかれましては、地域ケア圏域会議や自立支援・重度化個別会議等の会議にて、専門職の立場から助言いただいたり、地域課題の解消に関わっていただいています。
それぞれの立場で、高齢者または地域住民の「健康」「介護予防」「地域づくり」を、多職種協働で検討されていますが、多職種連携により、委員の所属や分野における事業や活動に波及した効果や好事例があれば、もしくは、改善してほしい点があれば、今後の事業に活かしたいので教えてください。
薬剤師会:地域圏域会議に参加して、こういった困ったことがあるのだなと知ることが多い。、
それぞれの圏域で5、6名が参加し、情報共有を行っているが、多職種連携は十分ではないと感じている。薬局に来る人を相手にしているが、困りごとがあった時、いろいろなことを知っていて紹介できれば、こういった制度が活きてくると思う。いろいろな事業があると思うので、周知してもらえればと思う。最近、みさいやネットの情報が多くなってきており、生活状況など、役立つようになってきた。
病院:多職種連携としては、地域連携室が、地域ケア圏域会議に昨年より参加している。
福祉にかかる事例検討を通して、地域の解決方法を検討するなど、圏域での役割を再認識できるようになった。健康や地域づくりということから、多くの取り組みをしている。
- 中央図書館と連携し、癌の情報について、周知するコーナーを設けている。正しい知識が力となる。しっかりエビデンスがとれている255冊を市民に貸し出しもしている。6年目で認知もされてきている。
- ケーブルテレビと連携して、30分程度の番組を作成し、好評を得ている。
- 教育委員会からの依頼で癌の出前講座を市内3中学校で行っている。今後も継続する。
- 保険健康課:
Q.介護・フレイル予防のほか、重度化予防につながる目新しい健康事業があればご紹介ください。
:(圏域会議)保健師が参加し、保健師という立場から一緒につくりあげている。
(個別ケア会議)保健師と管理栄養士が参加している。助言というよりは参加して事例を共有し、勉強させていただいいる。ケアマネと連携が進んだら、それぞれの立場の専門性を生かせた個別支援ができるのではないかと思っている。
(重症化予防)健康づくりについては目新しいことってなんだろう。生きがいづくりに視点を持っていくことが大事。普段の日常生活を生き生きと生活すること。どんなふうにそれに寄り添った支援ができるか。また、若い時からの意識づくりが大事。地域活動に参加しましょう。
子供の貧困など食支援の広がりがあるが、若い頃から地域活動に参加して地域の中に溶け込んでいくことがこれから大事。
- 自治会・公民館:
Q.介護予防事業の参加者は徐々に増加する一方、高齢化等で活動困難者もあり、新規参加の獲得に頭打ち感が見えてきているようです。
地域や団体活動においても、人手不足により、日頃の活動ではご苦労であったり、ご奮闘されていることと想像しております。
元気高齢者と関わりながら増やす仕掛けが必要であると考えており、それぞれの地域で精力的に活動する、校区や地域、また、高齢者のグループ・団体、サロン、スポーツ団体や趣味団体でも結構です。地域に、元気な高齢者の集まりがないでしょうか。教えてください。
自治会:明倫 輪投げ、グランドゴルフ、男の料理(助成有で、1回500円)
鶴島 グランドゴルフ
元気な自治会はサロンを20人で行っている。
独居の女性で、夜は不安でたまらないと話す人がいる。
先日、行方不明の案件があったが、2500円程度(市が1000円を負担する等、いろいろな人に普及するようにして。)のGPSを使用していればと残念に思う。
公民館:30の公民館がある。いろいろな行事をする時、高齢者は交通手段の確保が難しい。
コミュニティバスは、フリー乗降があるが、通る経路が決まっている。便も少ない。敬老会をしたら、会場近くの人か、家族の送迎のある人だけが来る。実施するといつも苦情がある。敬老会も実施場所によっていろいろで、商品券(1,500円)を配るところもある。
成人式と同様にどこに住んでいても、同じ敬老会ができないか話しているが難しい。利用者を増やすのが難しい。高齢化で花いっぱい運動もできない。
明るい話では、市政20周年で、おばちゃんたちが、「地域もりあげ隊」を作って、沖縄の踊りを踊るなど、大人子供合わせて25人くらいのグループで活動をしている。
趣味のカラオケグループが年々増えて、様々な会や施設に歌いに行っている。歌うのが楽しいと言っている。お年寄りは「生きがい」とか、「行くところがある」ことが大事。
- 消防:
Q.昨年度の救急搬送件数とその傾向を教えてください。
また、昨年度末の会議において、救急車を呼ぶかの判断を困ったときは、♯7119で相談してほしい。宇和島市では30件前後相談があると報告していただきました。
♯7119の上手な利用の仕方や、好事例があればご紹介ください。
:令和6年度の出動件数5,463件、内、搬送5,002人 過去最多。令和2年は、かなり減った。(コロナの影響がかなりあった)
人口割にすると。宇和島消防は16人に1人、救急搬送されている。
年齢別搬送人員、搬送5,002人の中で、60歳以上が4,136人、全体の83%。今年に入ってから6月30日時点で、出動件数2,803件中、搬送2,478名。昨年を超えている。
高齢化率が40を超えているということは、これから出動件数は増加していく。これは全国的は傾向なのかなと思う。
子どもについては、♯8000。大人の症状は、♯7119にかけてもらったほうがよい。
愛媛県全体で♯7119にかかったのは、19111件。この内、宇和島が371件。月30件程度は消防に相談があることになる。
(♯7119利用者の声)
・夫が動けなくなった。救急を呼んでいいか。
・♯7119をかけて、電話口で話し方がおかしい言われ、救急車を呼んだ。
迷ったら、電話相談をすることが一つの手。周知の仕方に問題があると感じている。
軽傷の方は何度も呼ぶ方が多く、重傷の方はなぜここまで我慢したかなと思う。
以前は、軽傷の方が多かったが、去年の割合でいくと、5,002名中、軽傷38.3%、中等症44.2%と中等症が増えてきたということは適切な使用が増えてきたのではないか。
- 警察:
Q.高齢化の進行により、認知症高齢者が増加し、警察からの問い合わせとして、徘徊による迷子や認知症状による家庭内トラブルも増えているようです。
徘徊や家庭内トラブルのほか、高齢者に関わる事件や事故があれば、ご紹介や注意喚起をお願いします。
:高齢者の家への巡回は、生活安全課で行っている。5月から多くなってきている。独居の高齢者が自宅で亡くなっているケースが増加している。熱中症多く影響しているのか。安否確認も増加。死後、数日経っている人も出てきているように思う。安否確認を毎日することは困難。警察官も数が少なくなっている。巡回連絡を重視していたが、高齢者を見守る体制が薄くなっているように思う。
情報をもらい、家族に連絡をとったりしているが、十分にできていない。亡くなっている人の家族に連絡がとれないということも出てきている。こういった場合、検死手続きも倍の時間がかかるなど、他の業務ができなくなる。
徘徊には、予兆がある。通常とは違う行動をとるようになるが、家族は見落とす。
防犯カメラなどで追うが、追いきれないのが現状。GPSをもっていれば、リアルタイムで場所がわかる。ぜひ、機器を買う、貸し与えるような制度を構築してもらえれば、行方不明が激減すると思う。個人の権利の問題もあり難しいと思うが、そういう機器を活用しないと同時に2、3人を探すこともでてくる可能性があるので、検討いただきたい。
- 歯科医院:
Q.認知症基本法が令和6年1月1日に施行し、認知症本人の意向に配慮した施策が求められております。
歯科医院の現場として、認知症の方の受診は実際増えているのでしょうか?
実際に治療される中、困りごとや工夫されていることなど現状を教えてください。
宇和島歯科医師会:介助者や家族が連れてきている場合はよいが、本人だけだと、病院に向かうにも、今どこにいるかわからず、病院がわからない。と電話があることがあった。(2件あった)。こちらから、予約時間前に電話をしている。説明をしても、話が長かったり、何回も同じ話をしたりする。次の予約が入っている場合は少し困る。
北宇和歯科医師会:認知症の方の受診についてだが、開業時から高齢者は多い。今はかなり高齢者が増えた。認知症の方はそれほど増えたように感じていない。
なぜかなと考えると、元気な人が増えてきている。80代後半から90代くらいの人がピンピンしている。だんだんネットさんに認知症の方の所へ行ってもらったことがある。
病院に来る人は、認知症といっても軽い方なので、少し進んでいる人も、付き添いがあるので、病院での困りごとはあまり変わらないという感覚。
たくさん薬を飲んでいることが困る。抜歯の時は、お薬手帳やマイナで調べる。
施設に往診に行くが、特養では、意思疎通ができず、「抵抗」もある。家族の方から、歯がないので、入れ歯を作ってほしい(見た目の問題)と依頼があり、施設へ行くが、意思疎通ができず「抵抗」もある。わざわざ入れ歯を作る必要がない場合(施設に食事形態を確認し影響がないなら。)は、作らないこともある。作っても異物として認識されて、使用しない。
在宅は寝たきりの方が多い。診察時に体勢が大変(ベットに乗りかかって診察するため)。家族が無関心で、協力してもらえないと治療がうまくいかない時がある。必要最小限の治療に抑えている。緊急性がある時は、南愛媛病院にすぐ紹介する。
在宅でも施設でも、大事にしてもらいたいのは、「口腔内をきれいにしてほしい」とうこと。
- 民生委員・ケアマネの会:
Q.認知症になっても住み慣れた地域で自分らしく暮らし続けるために、認知症本人の思いを踏まえた施策につなげたいようです。
認知症本人の思いを聞かれる機会もあると思いますが、そのような声を教えていただく、若しくは、団体等の集まりの場で意見を伺う場を設けていただくことはできますか。
民生委員:独居が主だが、訪問して何度か話している時、初期の方では、「料理の味つけが濃くなった」とか、出てくる。最初は、軽く流して、周りの人にお願いし、気にかけてくれと話す。番城地域は近所づきあいがあるので、(近所から)やはりおかしいとなり、包括につなげるようにしている。認知症ではなく、高齢者訪問をしているといって訪問してもらう。
家族が離れていると、家族が親の認知症をなかなか認めてくれない。(家族が)1週間の休みを取って帰ってくるが、取り越し苦労だと飛ばされることがある。そうすると、周りが大変になる。その時に、また包括につなげる。民生委員は283名。4名欠員。今度11月末で、新しい民生委員と交代となる。現時点で、48名欠員。お年寄りはどんどん増えている。70歳くらいまでなら大丈夫だが、それを過ぎたら、地域の力を借りないとどうにもならない。なんとか隣近所と協力して思いを遂げさせたいが、施設やヘルパーさんにつなげるのが最近の傾向。
民生委員と保健師の話し合いの場はできるが、認知症の人ととは難しい。
このような会でつながりができると、新しい制度を得て、アウトプットしている。
今は、話の詐欺のシャットアウトができるということを民生委員全員が広めているところ。ここへ来て、みなさんの話を聞いて、ひとつずつ広めている。
ケアマネの会:「本人を中心にした支援をすること」に気を付けている。
認知症という言葉が広がって、「あの人は認知だから」とその人自身を表すようにいわれる。(認知症はその症状のことを言うのだが。)ケアマネが始めにすることは、生活歴を聞いて、その人の人生に焦点を当てるところから始める。エンディングノートや私の人生ノートなどを事前に作成していたら、役に立つ。
本人自身から聞く話としては、「認知症になるとかえって楽なんだ」という人もいるが、「自分のことは自分で決めたい」とか、食べるものに困っていることがある。本人の言葉に出てくることと、実際とは違うことがある。わかりにくいことがあるが、本人のペースにあわせて進めている。
意思疎通できない時は、ケアマネだけではできないので、家族から人生観を聞き、チームで本人の人生を推測しながら、決めつけず、修正していっている。
子が都会に出ている人が多い。外の人と会うと、認知症の人は元気になっていることある。そのため、子からは認知症ではないと思われる。ギャップに困る。
この時期は、エアコンの設定ができないなど、命の危険があることがある。
カメラを付けたり、GPSを持ったりする制度があればと思う。
今後の施策で認知症の人の意見を聞きたいということであれば、その家族など協力できるのではないかと思う。
- 福祉関係者:
Q.介護現場では、慢性的な人材不足に伴い、施設運営に苦慮されているとお聞きしています。
身寄りのない入所者の方について、亡くなった後の対応がスムーズになるよう、ご健在している間に、施設で工夫していること、または、取り組みがあれば教えてください
共済会:人手不足。本当に深刻な問題。動く人がいない。厚労省から、身寄りがいないことで入所や入居を断ってはならないとあるが、内容はかなり不透明。お金がある方は、ICTやGPSなど本人の意向でできるがそれも限界がある。後見人を付けることもうまくいっていないことが多い。全てを網羅することは、施設の工夫でできるものではない。それぞれの関係者がもっている余白をなくす取り組みが必要。
- 老人クラブ:
Q.自分自身の身に何かあった時のことを意識してもらうため、終活に関する普及啓発イベントを開催したり、終活ノートの作成・配布に取り組んできました。
今後において、配布にとどまらず、実際に家族で話し合う機会づくりにつなげたいのですが、効果的なアプローチ方法やきっかけの機会や場所があれば教えてください。
老人クラブ:(宇和島市が作成している)終活ノートは、内容が網羅されていると思う。
効果的なアプローチの方法⇒役員会で、終活ノートを話すと、知らない。→周知がされていない。できれば連合会、役員会で行政から説明したらよい。(内容がよいので。)
元気な高齢を増やすには、テレビばかりみず、団体に入って、いろいろな活動をしてもらうのがよいと思う。
各地区での高齢化率はどうなっているか。
包括:旧吉田町47.6%、旧三間町43.0%、津島町46.9%、旧宇和島市39.1% 吉田が一番多い。
- 宇和島市社会福祉協議会:
Q.社会福祉協議会では、令和6年度から引き続き、市民後見人養成研修を実施されているようです。
その研修の参加者状況、受講人数、年齢層、職種、今後市民後見人を想定してのものかなどのほか、社協として、研修終了以後に市民後見人になられた方にどのような活動を想定されるのか、養成後の取組みや考えられる課題があれば教えてください。
社協:後見人養成研修について、11月に23名が受講予定。男性8人、女性15人。30代、40代。看護師、保育士、福祉関係者、民生委員が受講。後見人不足で調整に苦慮している。講座の最後には後見人として登録するのか確認している。社協職員や専門職員がついて、一緒に業務を行っている。
取り組みや課題については、フォローアップ研修や、体験研修を予定している。登録者と被後見人のマッチングが難しい。
- 宇和島市社会福祉協議会:
Q.社会福祉協議会におかれましては、市内における住民主体の地域づくりに関わっていると伺っております。その地域づくりを主導する部署として、これから取り組んでいく、若しくは、仕掛けようとしている事業内容やその狙いを詳しく教えてください。
社協:一層の委託を受け実施している。
- 各中学校圏域
各コーディネーター同士が情報交換できてないので、今後の集約と整備を行っていきたい。
- 移動の問題
どの圏域でも問題となっている。行政、社協、専門職、みなさんと勉強会を行っていきたい。
課題を整理し状況を知ることが大事。
- 城東
まち歩きをしてみて、圏域が広いということ、フジ桜町店だけでは少ない。民間企業さん、小学校の廃校を視野に入れて、サテライト的な拠点整理ができればと思っている。
地域づくりの取り組みなどを宇和島ライフの活用、広報紙などの媒体を使って、広く周知できればと思っている。地域の居場所づくりを行っていきたい。
【総評】
- 保健所:委員の皆さんは、見識を広めていただき相互協力ができる組織ができればと思う。
- 宇和島医師会:人口減少が問題となっている。知恵を絞っても問題を埋めることができない。今後も連携を保ちながら、より一層頑張っていただきたい。よろしくお願いします。
② その他 連絡事項
- 警察:巡回連絡カードについて説明。交番や駐在所が家庭を訪問した時に記載しているもの。訪問活動が十分ではない。このような会で配布し、記載いただける人には記載してもらい、災害や行方不明事案に対応している。よかったら、記載してほしい。
- 包括:市民公開講座について、8月9日の案内。
- 自治会:救急時、「火事ですか?救急ですか?」と聞かずに、番号を変えたら、時間短縮できるのになぜ番号を分けないのか。(火事は少ない)と投げかけのみあり。
3.閉会
|